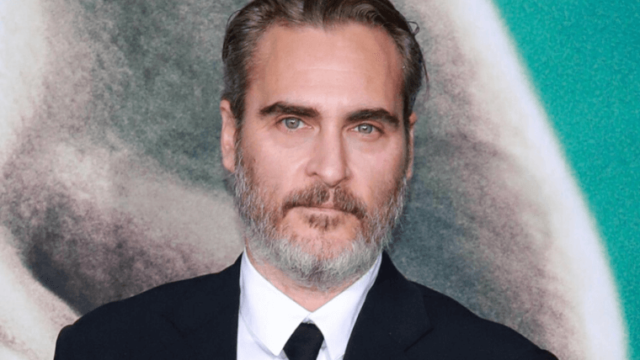こんにちは🌜
植物療法士のさとみ(@stm_nd)です(*ˊᵕˋ*)
みなさんは、身体を洗うボディーソープや洗顔は何を使っていますか?
わたしはずっと、お肌にも環境にも優しい石けん派です✨

石けんの起源はなんと3000年前の古代ローマにまで遡ります。
古代ローマ人は、水洗いや灰汁・植物で洗濯をしていました。
羊を焼いて神に供える習慣のあったサポーの丘では、したたり落ちた羊の脂と灰が雨に流され、それが川に堆積した土の中に、自然に石けんらしきものができたと言われています。
この“不思議な土”は、汚れをよく落とし、洗濯物が白く仕上がるとして珍重されました。
これが現代の「石けん」のルーツ。
石けんは宗教的儀式が思いがけずもたらした発見だったのです。
紀元前3000年代のシュメール(現在のイラク)の記録粘土板には、すでに薬用としての石けんが登場しており、塗り薬や織布の漂白洗浄に使われていたそうです。
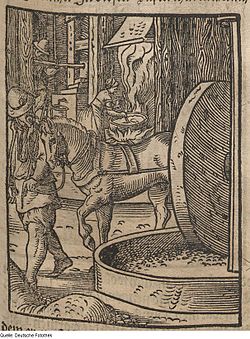
17世紀中頃の石鹸工場を描いた版画
一方日本では、洗濯には“むくろじ”の果皮や“さいかち”のさや、灰汁などが使われていました。
むくろじは、天然の界面活性剤を含む「ソープナッツ」「ランドリーナッツ」として、環境やお肌に優しいお洗濯洗剤代わりに、最近また人気が出始めていますよね♪
日本に初めて石けんが入ってきたのは戦国時代末期。
ポルトガル船のキリスト教宣教師たちによってもたらされました。
当時石けんは貴重品で、手にすることができたのは将軍や大名などの限られた人たちだけ。身分差の激しかったこの時代、庶民は植物や灰汁を使って洗濯したり、小豆や大豆の粉に香料を入れた洗い粉、ヘチマ、ぬか袋、軽石などで身体を洗っていました。
今では当たり前にあちこちで買うことのできる石けんも、昔は貴重なものだったのですね(*^-^*)
羊の脂から偶然発見された「石けん」ですが、石けんの作り方は、昔も今も基本的には同じ。
動植物の油脂にアルカリを加えて、加熱することで石けんになります。
人類は長い間、木炭や海藻炭をアルカリに使い、石けんを作ってきました。
やがて18世紀になると、海水からアルカリのカセイソーダを取り出す方法が発明されます。この発明によって、石けんは大量生産が可能になり、安値で普及していったのです🧼

石けんも人工的に作るものにはかわりはないのですが、70度から100度とあまり高くない温度で作られます。
また、使用して河川に流れても、自然界のミネラルと結びついて
「脂肪酸Mg」
「脂肪酸Ca」
となって魚のエサになるなど、石けんの長い歴史の中で、その安全性が確認されています。
また、環境に優しく生物にとって安心・安全であるにもかかわらず、ウイルス破壊能力は合成洗剤の1000倍にもなります。

ドラッグストアに行くと、最近はボディーソープやチューブ式の洗顔が主流になっているのかな?と感じますが、
石けんはパッケージの面でもプラスチックを減らすことができますし、
保存の点でも、基本的に化粧品やシャンプーなどは水分量が増えるごとに反比例して保存期間は短くなってしまいますので、
水分量が少なく固形に近いものほど、保存料や防腐剤などお肌に良くない成分を使用する必要性が少なくなってきます(*^-^*)
ラヴィステラでは、天然100%、ヴィーガン、パームオイルフリーにこだわった美容石鹸を5種類ご用意しております🧼
こちらもぜひご覧くださいね。



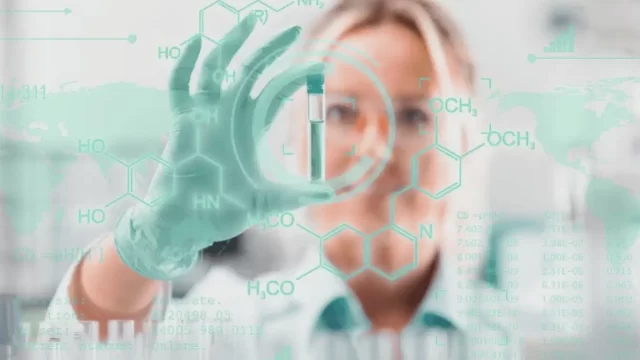






2880-x-800-px-4-scaled.webp)